|
夜になっても蓄えられた地熱の衰えはなく、じっとしていてもじっとりと汗がにじむようで
目の前の空気も淀んでいるような空が古ぼけた窓枠を通して見て取れる。
クーラーなんぞ、この安宿に備え付けられているはずもなく、
煤けた壁紙がカサカサと音を立てるすきま風がかえって都合がいい程だ。
実のところ、この宿に着いたときには目に付いた壁のしみも、
耳障りな水の滴りも、今はオレの外側で意味をなさずにとどまっている。
生物なんてゲンキンなもので自らの興味が他へうつればおのずと
古いものは消されていくんだろう。
次第に無口になっていく狐様はどうやら空腹が故だったらしい。
宿の主人に食事を頼んでひとごこちつくと、寝台に座って実に幸せそうに
ため息をつきやがった。
「ハラ減ったからって機嫌悪くなるなんざーガキだな」
答えが返ってこないと思ったらどうやらオレの背中が気になるようだ。
「飛べるのか?」
「あ?」
「飛べるのかお前」
「まぁな、あんまり滞空時間は長くねーけどな」
「へえ、すげーな。オレも鳥だったらよかったのに」
「お前はどっからみても狐だな・・・どこの生まれだ?」
「知らん」
さりげなくヤツの隣に移動してみる。
オレの座ったはずみで寝台が撓んできしんだ。
余波で上下している蔵馬を見るに、やはり体重はそんなになさそうだ。
(これなら気絶させて運んでもなんとかなるかもな・・・)
オレの不埒な考えを知ってか知らずか、ヤツは琥珀色の瞳でちらとオレを見上げて
尻尾で布団をなでた。
「オレは・・・気付いたらこの姿だったし・・・まわりに誰もいなかった。
そんときオレがここに居るって事とまわりの植物の匂いがしてただけで
その前のことも覚えてない」
考えてみればコイツがここまでの語数をオレに喋ったのってはじめてかもしれねえ。
妙なことに感動をおぼえつつ、先程より随分と大きくなった感情の目でヤツを見渡してみる。
肌も髪も、装束から伸びたあらわな二の腕も、その装束でさえも白い。
ゆらゆらとうねる耳の綿毛はオレの翼の色をとかしこんで
薄墨のように見える。
触れたか触れないかの距離で手をのばすと、ついと顔をあげたヤツの造作に今度は見とれる。
「お前は・・・動物の転生妖怪かもな・・・」
「転生?」
「ああ。動物でも植物でもある程度以上の年をとったり、術を使ったりすると
妖怪に転生することがある。その場合、以前の生の記憶は残らないはずだからな。
自分が何者だったかわからないままにただ魔界におとされるんだ」
誰かから聞いた遠い記憶が驚くほど流暢にオレの口から滑り出る。
もう憶えてない、思い出すのもしんどいほどの遠い昔。
オレもただ、ここに在った。
ふと、ひどく自分とヤツが重なる。
掌を合わせるときっと同じ体温、同じ形であろうと思えるほどに。
「それはいつのことだ?」
「100回目の満月を数えたけど、あとはもうわからない」
10日に一度の魔界の満月は、まだ一歳にも満たないこの妖狐をどのように照らし出したのか。
自分への哀れみか、この狐への執着かわからないままに頬に手をかけると、
桃のような柔らかさと産毛の触感に一気に熱が上昇した。
「それで」
身体の重みを半分蔵馬にかけ、耳に口をつけて囁いてやる。
「お前はどうやって生きてきたんだ?」
肩の丸みにあわせるようにして手の甲で白装束をすべりおとすと、まだ誰も踏んでない新雪の世界。
100回の満月?その若さと生気が皮膚をの奥に灯っている。
掴み所のない妖狐といってもこの通り、わけもなくオレの手の中だ。
コイツはコイツ、オレはオレ。コイツはオレの獲物、オレは狩人でコイツは狐だ。
頭に血がのぼってとりとめもなく思考がぐるぐるとめぐり、
そのとき「あ」と蔵馬は小さく声をあげた。
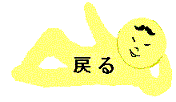

| 
