|
「ゆっくり手ぇ上げてこっちを向け」
その声が意外に細かったのでおそらくオレは怪訝な顔をしていたにちがいない。
「お前、面白い顔してんな」
対面したそいつの第一声がこれだ。
オレとしたことが不覚だった。
こんな化狐の細っこいヤツに後ろをとられるとはマジ自分に腹が立つ。
そいつはオレに変な形の剣を突きつけたまま、(ちなみにオレは両手挙げたまま)
しゃべれ、というようにちょいちょいとそれを動かした。
「お前、ここで何してんだ?」
「お前がそれをいうか?」
「ここの警備兵か?」
「・・・そう見える?」
「見えない。むぐ」
「じゃー聞くな!・・・ってもの食いながらしゃべるな!」
「旨いぞこれ。お前も食うか?」
「・・・」
よほど腹がへっているらしく、片手に持っている食堂から奪ってきたらしい
食べ物をせっせと口に運んでいる。
顔の頬から顎まで食べカスがいっぱいだし、返り血は白銀の髪から衣までべったりで
みるからに汚い。
背はオレよりいくぶん低いくらいか。
狐といっても銀狐らしく、全体的に色素が薄くて華奢に見えるが、
いつかどこかの祭礼で見た舞踏手のような体格をしている。
「お前、ケガしてんじゃねーか?」
返り血と思っていたものが先ほどより面積を増しているのをみて思わず口をついた。
「ああ・・・ここかな」
左腕を持ち上げてその裏側の傷をくるりと布でまいたヤツはちらりとこっちを伺って
「手当て得意なのか?」と言う。
「まあこんな商売な以上な」
「手当てしてくれても戦利品はわけてやらんぞ」
「かわいくねーガキだな!」
「蔵馬、だ」
「へ?」
「さて・・・と。」
「うぉぉい!会話はキャッチボールだろお!!」
オレが同業者だと知り、ほっとしたのかなめられたのか、
ガチャガチャとオレに背を向けて盗品のチェックをしているらしい銀狐・・・
蔵馬っていうのか?を見ているうちにふとあることに気付いた。
「お前、盗ったのそれだけか」
訝しげな表情で振り返ったヤツをここぞとばかりに得意そうに見下ろしてやる。
背が高いとこういうとき役に立つ。(こういうときだけか?)
「お前、ここんちの隠し倉庫しらねーの?」
「もし」
「あ?」
ちょっとびっくりした。間髪いれずに言葉を繋がれたのでややテンポを崩される。
「どこにあるんか教えてくれんなら分け前10分の1やる」
「お、お前・・・それはオレのセリフだぁー!」
「何で?ここんちに先に入ったのはオレだからここのものはオレのもの」
こいつは・・・どこかのいじめっ子か・・・
何とかその後1/5分譲させることを承服させて、オレ達は地下の倉庫に入った。
全く情けねえ・・・
「へぇー台所の裏の隠し階段か・・・古典的だな」
「そんな古典的な隠し階段に気付かなかったのお前だろ」
「さっき古典的な落とし穴トラップにひっかかったの誰だっけ」
「う。。。」
倉庫前の門は術除けの呪が施してあるようだ。
妖気をつかった術では開くのは難しそうだ。
こういうときは物理的にあけるしかない。
「それ、自分の羽?」
「ああ。これで妖術や発破で開かない錠は物理的にサムターンを回してやればいいんだ」
「へえ」
「オレの意志にしたがって中で自由に形をかえることができる」
「ふーん」
腰をかがめて鍵の中の音を聞いているオレの横にぴったりはりついて
オレの手元をじーっと見つめている。
本当にガキ臭いやつだ。
「お前、すげーなー」
カチャ。
お褒めの言葉をいただいたそのとき、鍵が開いた。
「さーてお宝お宝・・・」
小生意気なガキに一度褒められたからって機嫌がよくなる自分が悲しい。
元々愛想のいい奴がいいことしても何も感じないが
もともと嫌な奴や無愛想な奴が何かいいことをしてくれると100倍くらい
印象にのこる。トクだよなー。
倉庫の中は暗くてカビやほこりの匂いで充満している。いや、他にも。
「何だーこれ?」
足をとめた蔵馬が小さく呟いた。
さくさくと霜柱を踏みしだく軽い足音の主からは尻尾を振るごとに
色々なヤツと主自身の血の匂いがしてくる。
「・・・ったく下劣野郎め・・・どこが宝だ・・」
隠し倉庫内にあると思った宝の山は夥しい数の生体標本だった。
それらの薬物の匂いと生臭さが今も頭の芯に残っているようで気持ちが悪い。
「おもしろかったしいーじゃん」
コイツもコイツでその中から取って来た馬頭妖怪の耳の標本を弄びながら
ハナウタなんぞ歌っている。
「そりゃお前は金目のもんあらかた盗めたからいーよな・・・」
「うん」
うん、じゃねーよ。
激しく無駄足。徒労。骨折り損のくたびれ儲け。
オマケに変なガキとも知り合ってしまった。
人の話をまったく聞かないヤツ。勝手でいいたいことを言い放題なヤツ。
親の顔が見てみたいぜ。
「おい、蔵馬これからどう・・・」
少し照れながら初めて名前を読んで後ろを振り向いた時、ヤツはもう消えていた。
その時の気持ちをなんというんだろうか、
言葉では言い表せない、しいていうならからっ風。
墨をながしたような空を切り裂いて、粉のような雪が舞い始める。
ヤツの耳の綿毛にも似て、オレの翼にふりかかってきれいに結晶になってすぐ消えた。
そしてその瞬間の色をなんというのだろう。
自分の記憶の中からそれを探し出す時間、オレはまぶたの冷たさを感じていた。
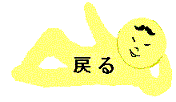

| 
