|
首縊島はミニマムな島だけあってホテルの壁の厚い部屋にあっても
木々のざわめきにまじり、かすかに海の音が聞こえる。
となりの部屋からは誰かのいびきらしき音も漏れている。
(おそらく幽助だろう)
カーテンの隙間から月明かりがもれ、目をとじていても感じることができるほど明るい。
目の内側で光が色々な形をつくってゆく。
武術会がはじまって何戦かを経た。
彼は安全策と情を重んじる戦い方を努めてしてきたつもりだったが
身体の端々で何かが声をあげている事にとっくに気づいていた。
そんな生ぬるい戦い方はやめろ、と耳の奥で唄っているものがある。
ふとしたはずみでひどく凶暴な気分になる。
片方の脳ではそんな自分をひどくもてあますというのに。
そしてこの波の音。
魔界の荒れた海を思い出す。
あれは誰といた季節だっただろう・・・?
(海水でべたべたしているからだを舐められてお前は全身しょっぱいなって言われたっけ・・・)
それしか憶えてないヘンな記憶・・・
ぱた、と彼は何度目かの寝返りをうつ。
まだ癒えていない傷がシーツに擦れるがすでにそんな感覚も遠い。人間としての感覚が。
赤みをおびた細い黒髪をくしゃくしゃと肩に巻き込んで、蔵馬は二度まばたきをした。
二重の幅のひろい瞼が月光でうっすらと青みをおび、濡れたような艶を放っている。
「眠れないのか」
突然後ろから声をかけられて彼は目をさらに大きくひらいて寝返りをうった。
「飛影も?」
「お前がばたばた動いているから目がさめたんだ」
「そんなデリケートだとは知りませんで。すみませんでしたね」
皮肉をたっぷりぬりつけた科白を微笑んで投げつけた。
飛影はそれには答えず、
「傷が痛むのか」と問う。
「なんだか・・痛いというか・・・全身がむずむず落ち着かないかんじかな・・・なんでだろう?」
「オレにわかるか」
「あーそうですね 言って損した」
沈黙が落ちる。
「実は」
しゃら、と薬指で布団を撫でる。
「大会がはじまってから日がたつにつれて痛みとか五感の感覚が薄れてきた気がする。
味覚も・・・あまり感じられない・・・香辛料とかのすごく強いもの以外は。」
ふうっと飛影が息をついたように感じられた。
「魔界の食い物はみんな味がドギツイからな」
「それって・・・オレ、妖怪に戻ってるってこと?」
ベッドからおりて窓に寄り、ちょっとカーテンを引っ張ってみる。
月はほぼ真ん丸い。あと少しで満月というところか。
月明に見入っている蔵馬を横目で見ながら飛影もベッドをすべるように降りてきていた。
「戦闘の感覚が戻っているんじゃないか。結構なことだ」
その声が予想以上に近かったのでやや驚いたが、蔵馬は振り向かないで「はは」と笑った。
相変わらず気配を感じさせない。簡単にバックをとられてしまった。
「身体がね」
蔵馬の首すじに飛影の呼吸が感じられるほどの距離だ。
「痛だるいようなぶんぶんふりまわしたくなるようなかんじで苦しいんです」
くるりと振り向いて飛影の逆立っている髪の先をそっとひっぱり、
薄く笑いながら提案をしてみる。
「どうにかしてくれないかな・・・この痛み」
横頬から耳たぶをぱくりとくちびるで撫で上げる。
「皮膚の下から何かが突き上げてくるみたいで・・・暴れたい」
下唇を耳に押し当てたまま静かに呟くと飛影の身体がびくっとして
やや眉根を寄せた彼が蔵馬に視線を合わせてきた。
「サカリでもついてんのか」
「・・・どうでもいいです・・・いつかの続き、します?」
その言葉で飛影はカッと顔面を紅潮させたが蔵馬はそれには気づかないふりをして
頬と顎に手をやり、舌で飛影の上唇をぺろりとなぞった。
一瞬のスキをついてぴょんっと蔵馬から離れた飛影はめずらしく狼狽したふうで
「あの時は・・・オマエが頼んだから・・・」とベッドに荒々しく座る。
「未遂でしょ、しかも。大体妖怪なんだからモラルとか貞操とか関係ないんだし」
「オレは」
こういうときの彼はとても黒龍の使い手には見えない。
「誰かの代わりはゴメンだ」
蔵馬は首と肩をくるくる回していた。
「あーほんとなんか身体へん・・・。誰かの代わり?はは、何言ってんの飛影。
誰かの代わりって言うのは特別な誰かがいる時に使うもんでしょ。
オレはあんまりそういうの作らないタイプの妖怪だったし・・・ぇ」
回していた腕が一瞬にしてびくっとと止まる。
「だってオレは・・・」
蔵馬の視線が宙をさまよい、激しく言い募った。
「違う・・・オレは・・・アイツの・・・」
海の音が呼び起こさせる記憶。浮かんでは消える妖怪たちの記憶。
そして唐突に蘇るその影。
「お前は全身しょっぱいな・・・」
「・・・そうか黒鵺だったんだ・・・そう言ったのは・・」
後ろから自分を包み込む優しい手。
笑うと皺のできる豪胆で快活な顔。
思い出はそのつまっている袋を針の先ほどでも破くと次から次へと止めどもなく
あふれ出し、現実の蔵馬を支配する。
指の先まで追慕に染まって、蔵馬はベッドに飛び込んで羽布団を頭までかぶって
ネコのように丸くなった。
「おい・・・」
飛影が驚いて見ている気配がする。
「情緒!不安定なんだ!」と叫んだ蔵馬は自分の手を握り締めていた。
この手を今度はもう離さないと・・・
もう二度と失いたくないからオレは彼女を守るために・・・
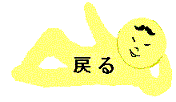

| 
