|
夏の日々は、いつ終わるとも果てるともしれないように、
私の絵も日増しに精緻になりながら、その完成はまったく見えないままで、
今日も今日とてあの場所へ足は自然と駆けていた。
ふと何かわからない思いに心がざわめいた。
それは銀狐が膝から下を下生えにうずめながらちょこんと座ってこちらをみているという
はじめてのことに、であろうか。
「やあ今日もいい天気だね」
いつものように無表情を崩さない銀狐は言った。
「わかったよ。こいつら、アンタにおびえてるんだ」
「!」
妖怪として永く時を生きてきて、あまりもう驚くようなことも
世の中になくなったと感じていたのに、この人里離れた茫洋とした樹の海の中で
私は虚を突かれたのだった。
「タチアオイが」
「えっ・・・」
「アンタは血の匂いがするって」
「・・・」
「オレはさ。別にいいんだけど。コイツらが怯えて何も喋ってくれないのは困んの」
「そうか・・・銀狐さんの能力はマジもんなんだな」
ぴこ、と耳だけをせわしなく動かしながら彼は小首をかしげる。
おそらく遠くで風が鳴っているからだろう。
「だってそうだろう?植物を使えば労せず敵の情報を掴めることもあるってことだからなぁ」
そうか、という表情がなにかと乏しい彼の顔からひろうことができる。
「そっちに座ってもいいかい?」
返事を待たず、朝露の残る虎杖の葉を踏みしだいて
彼に食べさせるつもりで買ってきた菓子を取り出しながら花をよけて腰をおろした。
風がふけばすずらんの香りを想像できそうな隣の白いけものは、
予想に反して何のにおいもしない。
(本当に狐なんだな・・・)
においがあっては単独で狩をするときに邪魔になる。
それが群れない肉食動物の常だから。
今までで一番近い距離にある彼の顔はしかし黙ってこちらをみている。
「私は風景画を描くのが好きだけど」
両手を土の中に差し込んで、掬い上げてみる。
「やっぱりそれじゃやってけないんでね」
湿っていて重みのある土。どっさりと栄養が詰まっているのだろう。
私は自分の表情を上手く出せている自信が無かった。
「本職は戦化粧師兼、戦闘絵師なんだ」
「それって何?」
「聞いたこと無いかな」
「うん」
どうやら本当に興味を持ったらしい。
もっとも、そうでなければ聞き返してきたりしないだろう、この狐は。
「戦士や兵士に化粧を施すことによって妖力をアップさせる技術が戦化粧。
大きい戦争のときなんか、一晩で何百人にも描かなきゃいけなかったりして大変なんだよ」
「へぇーー」
「戦闘絵師は武器になるようなものを絵に描いて、それを妖気で実体化させることができる。
もっとも、描いた絵師の妖力によって制限がかなりあるが」
「どんなの描いたことある?」
「変わったところでは、その城主の妻とかな」
「強かったの?」
「城主の百倍くらいおっかない奥さんだったよ」
「ふーーーん」
ここは笑うとこなんだが・・・
「戦化粧師や戦闘絵師のつかう染料は全て血からできてる。私の体にはきっとその臭気がしみついてしまってるんだろうな」
頭の中を回転させつつも私は自分がなぜこんなことを、
自分の仕事の話なんぞを必死にしているのか、実はさっぱりわからなかった。
おそらくは。そう・・・おそらく。
「そっか・・・」
言い訳をしたかっただけなのかもしれない。
となりの獣の警戒を解かせて、自分への信頼を、その関係を得たかったのかもしれない。
「とりあえず、そのニオイを消せばいいんだな・・・」
銀狐は独り言とも、彼の喋らない咲き誇る友人との会話ともとれることを呟き、
こちらをちらりと見ると軽く目をつぶった。
ここまで一気に話した私は胸の動悸を抑えつつ、
彼の様子をみて落胆したような、ほっとしたような奇妙な気分を味わい、そして。
音も無く突然後ろから差す影に驚いて飛び退り、180度体を反転させた。
普段後方支援ばかりしているから、とっさの反応が鈍くなっているのかもしれない。
「ああ、動くな。じっとしていろ」
意図せずとも尊大な銀狐の声が抑揚無く後ろから響く。
突如として私の後ろにあらわれたガサガサとした巨大な笹のような樹は、まるで私の傘のように
上からこんもりと枝を頭上にさしかけ、何かを待っているようにも思える。
間違いなく、今までここに無かったものだ。
「それはな、殺菌・消臭に特に良いものだ。それと共にいればアンタも好かれるようになるさ」
(誰に好かれろって・・・?)
実に満足げに言い放つ彼に、おいそれと反論もできず、
私は驚き呆れながら心の中でごちるしかなかった。
さっきから肝をつぶすような事態が連なりすぎて、
銀狐の後ろに黒い翼がふわりとみえたとき、私はもうあまり心を動かされずにすんだ。
「今度は何を呼び出したんだよ、蔵馬」
その翼はざっくばらんな調子でこちらに声をかけてきた。
「有加利というらしい。自分で言ってるからな。それより遅かったな、黒鵺」
「・・・遅かったな、だとおぉぉぉぉおお!!」
「お前を待って十日以上もつぶしてしまった。北の砦に向かうんじゃなかったのか?」
「お前が突然いなくなったんだろうが!!オレはこの十日ずっとあちこちお前を探し回ってたんだよ!!
それがこんなとこでおまけになんか怪しいオッサンと仲良くなってるし・・・!!!」
「絵描きさんだ。絵がすんげー上手いぞ。お前と違ってな」
「がーー!!どーゆー意味だ!!!」
「黒鵺も、描いてもらったらどうだ?そのおもしろい顔」
「%△○◎・☆▲○◆!!!」
「ここの植物とも話ができたし、遠回りも案外意義深いものだな」
したり顔で頷きつつ、銀狐は黒い翼の若者につと手を伸ばす。
憤懣やるかたないといった表情の黒衣の若者はしかしおとなしくその手をとって狐を立たせてやった。
私はひたすら瞠目していた。
はじめて、孤高の野生動物が人に体をすりよせた瞬間を見たような、
名状しがたい複雑な驚きという理由で。
相方の流麗な銀髪を無造作にそして繊細に指先でもてあそびながら黒翼の者は
いくぶん怒りを鎮めながらなおもその髪の主に話しかける。
「オマエ、飯どうしてたんだよ」
「ん?絵描きさんにもらってた」
瞬間、ものすごい殺気を感じたが、私が後ずさりしようとしたときにはもう遅かった。
「オイオッサン」
顔が、近い。
「何かな」
「メシの見返りに、アイツに何かさせたんじゃないだろうな」
「あの狐さんが大人しく私のいいなりに何かやってくれると思うのかい?」
「・・・・」
「・・・・」
「それもそうだな・・・」
あやうく襟首まで掴まれそうな視線を外してくれたので私はほっとした。
こいつは、あきらかにカタギじゃない。
「そうか、悪かったな・・・アイツ性悪だけどバカだからさ・・・ダマされてそうでつい(ごにょごにょ)」
「彼は、蔵馬というのか」
「アイツ、名乗りもしてねーのか」
しょーがねぇな、といった感じで笑った彼は、するどい目が細くなると
ひどく人懐っこい顔をすることに気付いた。
「君は“くろぬえ”だろう」
「ああ、そうだけど・・・」
「時々、蔵馬くんが言ってたよ、君の名を」
「え゛っ・・・な、何て・・・?!?!」
期待と喜びに満ちた彼の顔に全てを悟った私はひとこと、
「忘れたなぁ」と言ってささやかな復讐をとげた。
こころなしか肩を落としつつも「世話になったな」と言って私に金を押し付け、
「アンタ、化粧師だろ?ニオイでわかる。なんかあったときに頼むぜ?」と囁いた彼―黒鵺―に
少し罪悪感を感じつつも、振り返りもしない小さくなる鮮やかな白い後姿と
黒い翼の距離に波立つ感情を禁じえなかった。
だから、手の中のキャンバスに描かれたそれは、黒鵺君にも誰にも、そして彼自身にも知られず、
私のためだけに存在しても許されるだろう。
それを目にするたび、いつもあの夏の森に帰ることができる。
古杉、立葵、白い花々、銀の狐、そして最後に描き加えたキャンバス下の有加利の樹・・・
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
黒鵺がでてくるとなんでいきなりギャグ路線になるんだろう・・・
いいなこういう人、ムードメーカーに一家に一台ほしぃ。
お気づきの方はいないかと思いますが、妖狐蔵馬さんはウチのねこ「ごま♂」をモデルにしています。
白くてね・・・わがままでいきなり甘えたりクールだったり、ときめきなのですヨv
普通、ネコは高いところに乗って降りられないとパニくって爪だして大変なんですが、
ごまはふつーに人間に「降りる」とかいって手を伸ばしてくるんです。
なんたる信頼関係!なんたる傍若無人!!
人間を踏み台にしか思ってないス!!
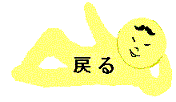
| 
