|
あの頃からそして今も彼は「理解できない」と言うのだろう。
感情の読めない声で。それなのに感情が伝わる生き物とはなんと不思議なものだろう。
「何のことだ?オレは帰るぞ」
「方法を教わったのは」
飛影の声になかば割り込むようにして蔵馬はあえて空っぽな口調になる。
視線は斜め上をむいてそこには天井の角が見える。
「妖狐のころだったと思う」
飛影の、窓に手をかけていながら息を殺して次の科白を待っている様を感じながら
蔵馬はあえて言葉を紡がなかった。
「・・・・」
飛影の息遣いが聞こえる。
発火地点を待っているようなそれでいて呆れているような。
はは、とやはり空虚な笑いを漏らして蔵馬は視線を下げた。
「飛影はあの時もそんな顔をしてたよ。オレが暗黒鏡を欲しいって言ったとき。
ああでももっと怖い顔だったかなあの頃は」
彼は彼なりに随分顔つきが変わったんだなと改めて蔵馬は感慨にふけったりする。
(今こんなことを考えるなんてオレも随分呑気だな・・・)
「やっぱり理解できない?」
今ここで飛影がイエスという返事をすれば
邪眼で森の中の往事を見ていたのを認めることになる。
さすがにひっかからないか・・・
心の中でごちて蔵馬はいくぶん面倒になった。
・・・試してみますか?とか聞いてみようかなー・・・
ぶん・・・っという音が聞こえそうなくらい身体をひねって
飛影は蔵馬に背中しか見せない姿勢になった。
「お前は一体何のためにそこまで必死なんだ?誰かのためだっていうのか」
「そうですよ」
即答した自分にいささか驚きながら蔵馬は椅子に腰を下ろし、
手を膝の上で組んで前傾姿勢になった。
蔵馬からも飛影が見えない。
「あの・・・女のためか・・・?」
「オレはね飛影」
ゆっくりと一つ一つ言葉をひろうように喋る。
「全然足りないんだ。あの人の全てに。あの人がオレにしてくれたこと全てに。
そしてオレがしてしまったことに。」
心の平均律が乱れそうになるとき人間はどうやってそれをおさえるんだろう。
誰が正確な鼓動をきかせてくれるのか。
その心で心を包んで。
「オレが殺したんだよ あの人の子供を」
飛影相手に何を話そうというのだろう。ああ、でも。
「だからオレは何をおいても・・手段なんか選んでいられない」
誰に話すって言うんだ。他の誰に?同じ妖怪である飛影しかいないじゃないか。
日常抑圧し続けている感情は一度吐露しはじめるととどまるところを知らないのかもしれない。
蔵馬という存在には小さすぎる南野秀一という肉体の器。
そのひずみは自分の感知しえない所でどんな影響をおよぼしているのだろうか。
「朱雀の件ではオレたちのことが魔界に知れ渡った。少し考えただけでも十分に危ない。
それなのにオレはS・A級の妖怪はいうにおよばず今のままじゃ戸愚呂にだって勝てない。
君もだろう飛影。邪眼をつける前のレベルに到底まだ戻れないだろう?」
飛影ははすかいに蔵馬をみている。かすかなぴりりとした感覚が蔵馬の肌をかすめる。
「オレは強くなるためならなんでもする。今はそれしかない。自分のためじゃない。
飛影にはわかってもらえないだろうけど。」
ふん、と鼻で息を吐きながら飛影は口をひらいた。
「オレは母親に捨てられた妖怪だ。お前みたいな感情は微塵も持ち合わせていないな」
身を躍らせて飛影はすっかり日の沈んだ街へ飛び降り、
その闇はあっという間に姿をのみこみ同化していった。
もう夏を感じさせない夜の秋風がどどうと部屋のカーテンをゆらした。
顔の前で組んでいた自分の掌をひらいて蔵馬はつくづくとみつめる。
男らしさのない、かといって女性的にふっくらとはしていない肉のない節のめだつ細い指。
南野秀一という人間の指。
かつてのものを鷲づかむような鋭い形状の手はもうない。でも。
昔は汚れることが嫌いだった。
だから自分は頭を使うだけ。言い寄ってくる奴らにすべて汚い仕事をやらせていた。
銀髪の妖狐という清冽な容姿のおかげか部下や恋人には困ったことはない。
血で汚れるのも泥まみれになるのもいやだった。
でもあの人がオレのために流した血、いつも自分を気遣って動き回り、仕事をしたあとの掌。
どす黒くて汚いのに。
鈍く光っていた。
そう、光っているんだ。
「飛影」
声にだして呼んでみる。
「それでも君はずっとずっと雪の国に焦がれ続けていたじゃないか」
<泥だらけで鈍色・完>
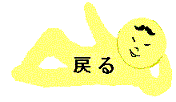
| 
